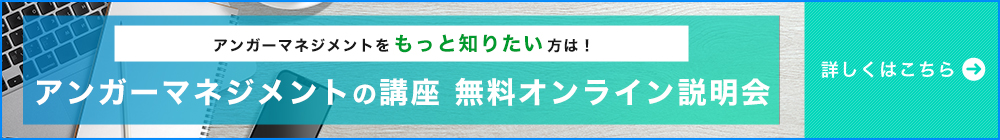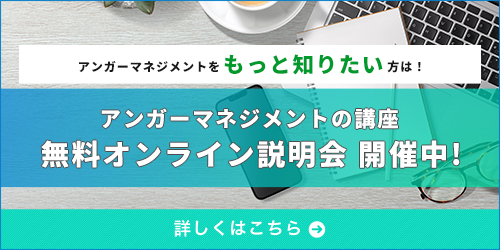コラム
アンガーマネジメントが「たけしのニッポンのミカタ!」で紹介されました
昨日、テレビ東京の「たけしのニッポンのミカタ!」にアンガーマネジメントが登場しました!
番組冒頭では、「近隣諸国の挑発的な言動に対し、日本は弱腰外交なのでは?グローバルな時代を迎えた今だからこそ、論理的に話して伝えなければ、ご近所トラブルはもとより、国だって滅ぼしかねない!?」とうテーマが掲げられ、それぞれの専門家の話が紹介されました。
興味深かったのは、怒りと脳内物質のお話。
アンガーマネジメントセミナーでも、セロトニンを出すワークをいくつかご紹介しているのですけれど、今回はその仕組みも解説されていました。
怒りは脳の「扁桃帯」にどれだけセロトニンが分泌されるかでその強度や頻度が変わってきます。セロトニンとは怒りや恐怖をコントロールし、心のバランスを整える作用がある神経伝達物質です。つまりセロトニンの分泌が多ければ攻撃性が弱く、少なければ攻撃性が強いという事になります。
そして日本人は、残念ながらセロトニン分泌を抑える遺伝子を持った人の割合が80%と、諸外国に比べ高いのだとか(ちなみに中国は75%、米国は53%、ドイツ43%、南アフリカ27%)。
日本人は外国人と比べて自己主張しないというイメージがありますが、もしかしたら腹の中は表現し切れていない怒りで一杯なのかもしれません!
それを踏まえ、じゃあ「どうやったら正しいけんかが出来るのか」というまとめのパートでアンガーマネジメントの登場です。
弊協会代表の安藤が、アンガーマネジメント体験クラスで下記3つのポイントをご紹介しました。
① 怒りに「反射」しない
「反射的に何かを言う、反射的に何かをする」と、相手も感情的になって論理的な議論ができなくなります。つまりこの「反射」を抑えるのがポイントで、抑えるのに時間はたったの2秒。テクニックでは「コーピングマントラ」という「自分を落ち着かせる魔法のフレーズ」を紹介しました。ムカっときたらこのフレーズを自分にいい聞かせ、怒りが爆発するのを防ぎます。
② 怒りを感じたら、点数を付ける
カチンときたら、その怒りに0〜10段階で点数を振って下さい。怒りを点数化することによって、自分の怒りを客観視することができます。できればこの「怒りを感じたら点数を付ける」を2週間続けてみて下さい。必ず同じ出来事に対しても点数に差が出て来ます。そうすると「あの時の怒りは、あんなに強く怒る必要はなかったんだ」と相対的に怒りの点数が低くなって、結果的に怒りにくい体質になります。
③ 喧嘩している時は、相手との共通点を探す
私たちは行為を持つ相手を見る時、自分との共通点を探すのに対し、敵意を抱く相手には違いを探そうとします。そうではなく、喧嘩している相手と自分に共通点がないか探してみましょう。
番組終盤で受講された方がこう感想を述べられていました。
「怒って無駄なエネルギーを使わなくていいんだ、と思った」
この言葉が全てを語っています。私たちが一日に使えるエネルギーも限られているし、生きている時間だって限られている。その中で、朝から晩までなりふり構わず怒っていたら、エネルギーと時間がもったいないですよね。
アンガーマネジメントは怒ってもいいのです。ただ、「怒る事と怒らなくていい事の線引きを自分の中ですること」そして「怒りを伝えるのに自分が怒る必要はないこと」を理解して頂けると、怒りの感情がとてもマネジメントしやすくなります。
今回の番組で、より多くの方にアンガーマネジメントが届くといいなと思います。
番組スタッフの皆様、聴講に来て下さった皆様、本当にありがとうございました!