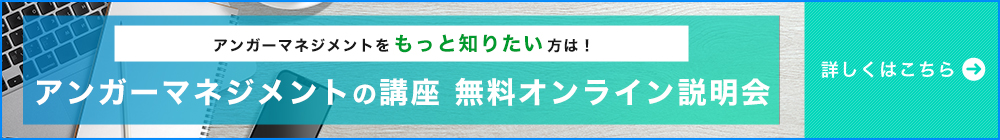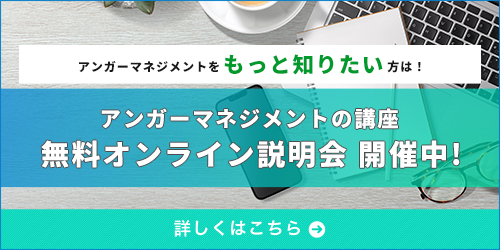コラム
学校
インタビュー
オリンピック
リーダーシップ
コラム - アンガーマネジメント
コラム - 時事
パリオリンピック開催記念 スポーツ×アンガーマネジメント松島理事にインタビュー
4年に一度のスポーツの祭典パリオリンピックが7月26日に開幕しました。スポーツとアンガーマネジメントには密接な関係があります。2022年に開催された北京オリンピックのスノーボード男子ハーフパイプの決勝で、金メダルに輝いた平野歩夢選手が、大技を決めたはずの2回目で点数に納得できなかったことへの不満をエネルギーに変え、逆転勝利を収めたことは記憶に新しいのではないでしょうか。まさに、アンガーマネジメントでいうところの「怒りのパワーをエネルギーに変えて」の大躍進でした。
また、スポーツ指導に携わる方においても必要不可欠なスキルの一つです。今回は公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)公認スポーツ指導者の更新研修も担当している、当協会理事松島徹氏にスポーツ×アンガーマネジメントの視点でインタビューを行いましたのでご紹介いたします。

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会理事 松島徹氏紹介
上場企業複数社にて人事マネージャーとして勤務。
現在も企業人事として勤務しながらアンガーマネジメントを伝える活動中。
マネジメント層向け研修や1on1など様々な階層別研修に登壇経験あり。
幼少期よりサッカーをプレーしており、長年の経験を活かして、プライベートでは少年サッカー団の子どもたちにプレー面やメンタル面での指導を行っている。
アンガーマネジメントに出会う前は、サッカーの試合中に審判の判定に対して暴言を吐いてしまったことで退場となり、チームも人数が少なくなったことで試合に負けてしまったという怒りで失敗したエピソードをもつ松島理事。先ずは、スポーツ業界での活用と選手としてどうアンガーマネジメントを活かせるかを伺いました。
スポーツ業界でどのように活用できますか?
選手が学ぶことで自身の怒りと適切に向き合い、不必要に怒りから生じる様々な問題を避けることが可能だと考えております。また、指導者が学ぶことで、昨今問題となっているスポーツハラスメントを回避することにも有効だと考えております。特に指導者と選手間でパワーバランスが生じているような場合、スポーツハラスメントが生じやすいです。指導者と選手には役割はあるが、お互いに対等な関係性を築く上でもアンガーマネジメントの観点から指導する際の声掛けなどを身に付けることは有効です。
選手が取り組むことで、パフォーマンスにどう影響を及ぼしますか?
怒りが必要以上に自身に向いてしまいネガティブな状況に陥ってしまう場合、プレーに集中できなかったり、誰か(審判やチームメートなど)に怒りをぶつけてしまったり、ものに怒りをぶつけてしまい試合に集中できずにパフォーマンスの質が落ちてしまいます。
逆に、自身のプレーに対して、失敗したことなどを次への改善点であるとポジティブに捉え、怒りをモチベーションにうまくつなげることでよりよい成績を残すなどパフォーマンスを高めることにもつながります。
試合中に取り組みやすいお勧めのテクニックはありますか?
イラっとしてしまうような場面で深呼吸※1をすることや、その場を離れ※2水分補給をする、集中するためにコーピングマントラ※3を唱えるなど様々なテクニックが実践できると思います。
パフォーマンスの質を上げていくためにもスポーツ選手がアンガーマネジメントを身につけることの大切さを感じました。そうした選手を育てていく為にも指導する側としてもアンガーマネジメントができている必要がありますね。昨年7月から「スポーツ指導者のためのアンガーマネジメント」講座が始まり、約1年間で各種スポーツ指導者が300名以上参加されています。指導者としてもどのように活かしていけるのか興味がある方が多いと思います。
公認スポーツ指導者の更新研修にかける想いをお聞かせください
日本スポーツ協会様の「No!スポハラ」という考えもありますが、当協会でも「怒りの連鎖を断ち切ろう」という理念があります。残念なことにまだまだスポーツ指導の現場では怒りの感情を適切にコントロールできずに指導をしている指導者もおります。我々が更新研修を行うことで、スポーツ指導者が指導の現場での声掛けやその他選手の考えを理解することなど指導力を上げることに貢献したいと考えております。
スポーツ指導者がアンガーマネジメントを理解し、適切に怒りの感情と向き合うことで、選手にもよい連鎖を生みだし、選手のパフォーマンス向上につなげていきたいと考えています。
様々なスポーツ指導者の声を直接聞くことができるため、他のスポーツ指導の現場からの学びも多い研修となっております。多くのスポーツ指導者に引き続き貢献してまいります。

チームスポーツと個人スポーツでの活用方法の違いはありますか?
チームスポーツと個人スポーツ以外に、競技内容など様々な条件によってことなるため、一概にチームスポーツと個人スポーツだけで分けることは難しいと考えております。ただし、チームスポーツであれば、人数が多くなれば、お互いの価値観も異なるため、価値観のすり合わせが必要になります。
個人スポーツでは記録を追求するために怒りが自身に向くことも多いかと思います。その怒りを自身で抱えすぎるのではなく、如何に自身が抱えている怒りを結果につなげるか、課題解決に目を向けることが求められます。
チームスポーツでも同様に怒りを自身やチームメートに向けるのではなく、チームとしての課題を解決するために生じている問題をどのように扱うのか、適切に怒りと付き合うためにもアンガーマネジメントは有効だと感じております。
中高生のクラブ活動で、効果的だと思われるエピソードはありますか?
指導する大人と中高生というそもそもの立場の違いからも指導者が上の立場になりやすく、指導者の考えに沿っていない苛立ちから声を荒げて生徒を責めてしまう。時には手を出してしまうといった問題につながる可能性があります。指導者がアンガーマネジメントを学び適切な怒りの表現方法を身に付けることは中高生のクラブ活動でも有効だと捉えています。また、怒り方は周囲の人を見て学ぶと言われています。指導者の適切な怒り方を側で見ている中高生自身も徐々に自身の怒りを言語化することができるようになるでしょう。その結果、自身がどのように考えてプレーしたのかなど適切に考えられるようになると、よりプレーの質を高めるためにどうしたらよいかなど解決思考で取り組むことができるのではないでしょうか。

最後に理事としてのご自身のビジョンや目標についてお聞かせください
自身としては、スポーツ指導だけではなく、各組織にアンガーマネジメントができる人を1人でも多く増やしていきたいと考えています。
そのために1人でも多くの仲間が増え、仲間が活躍しやすいように協会としての取り組みを様々なところで発信していきます。
アンガーマネジメントは本日お伝えしているスポーツ現場だけではなく、人と人がコミュニケーションをとる上で役立つ心理トレーニングです。
既に学ばれている方やこれから学ぼうと思っている方にも今後もわかりやすくアンガーマネジメントに触れる機会を増やしていくことが私の役割だと感じています。
アンガーマネジメントができる人を増やす。そのために協会として取り組まなければならないことに優先順位をつけて力強く取り組む松島理事。インタビューでは、様々な質問に応えてもらいましたが誌面の都合上、印象的だったトピックを抜粋してご紹介しました。
※1怒りを感じ浅くなっている呼吸をゆっくりと整え、身体の緊張をほぐすテクニック(呼吸リラクゼーション)
※2怒りの衝動を抑えられないと感じた時に相手に了承を得てその場から離れるテクニック(タイムアウト)
※3自分に予め考えておいた気持ちを落ち着かせる言葉を唱えることで冷静さを取り戻すテクニック(コーピングマントラ)
松島理事も担当している公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)公認「スポーツ指導者のためのアンガーマネジメント」はこちらhttps://www.angermanagement.co.jp/special/am-sports