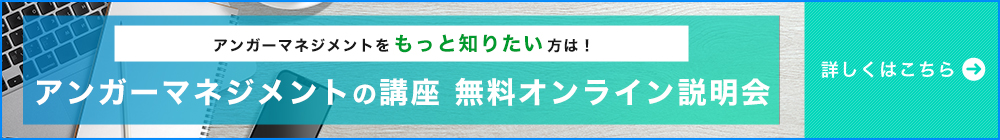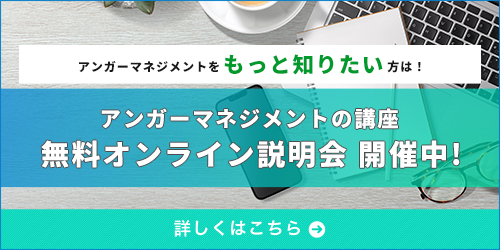コラム
ほっと・AM
コラム - アンガーマネジメント
アンガーマネジメント四コマ漫画
全国からこんにちは!
プレゼント
介護現場にアンガーマネジメントを
数年前から2025年は団塊世代が75歳以上になり、約5人に一人が後期高齢者となる、いわゆる「2025年問題」が各メディアでも取り上げられています。
介護が必要となる高齢者が増加する一方で、介護の担い手となる介護職員や訪問介護員の不足、自宅での介護の場合は、
担い手となる家族がいないなどが今後の大きな課題となると思われます。
今回は、「介護現場におけるアンガーマネジメントの必要性」についてお話したいと思います。
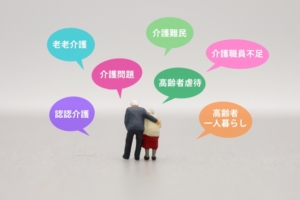
高齢者への虐待防止のために
令和5年度に、全国で家族や介護職員から虐待を受けた高齢者の数が18,000件あまりと、前年度を上回りました。
令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果|厚生労働省
まず、施設の場合ですが、どこの施設も毎日が忙しいです。
食事や入浴、排せつの介助、利用者さんの日々の様子観察、容体が急変した時の対応、場合によっては看取りケア…
と休む間もない職員さんが多いのではないでしょうか。
また、訪問介護の現場では、訪問介護員さん一人で利用者さんのケアを担当します。
食事の仕度や居室の掃除、はては通院の準備やお薬の受け取り等、短い時間で行う事が多く、
それを一日の間に何件も受け持ちます。
施設においても、訪問介護においても人員不足になってしまうと、今の人員でカバーしなければならず、
十分な休みが取れないために疲労が増す、利用者さん一人一人とゆっくり関わりたいと思っても
それが出来ない事のジレンマがある…
という事が重なり、だんだんイライラが増してしまう、という事があります。
介護の仕事でイライラする時(夜勤編)
この件について、アンガーマネジメントの視点で考えてみます。
結果、ほんの些細なことがきっかけとなって、「ついカッとなって」施設や訪問先での暴言や暴力となり結果、
高齢者虐待となってしまう事が多いように思われます。
家族による虐待についても同様に、自宅で介護をする人が誰にも相談できず、自分一人で介護を抱え込み、
疲労が増し、結果イライラしてしまう…という事が考えられます。
アンガーマネジメントは「怒りで後悔しないこと」そして「自分の中で怒る事と怒らない事の線引きをすること」
を目指します。
アンガーマネジメントは「心理トレーニング」ですので、続けることによって、無駄にイライラせずに
介護にあたることが出来るようになります。
介護する側がアンガーマネジメントを実施し情緒が安定していれば介護をされる側も
安心してサービスを受けられるという事もあります。
様々なケアが必要な人を多職種で支えるために、良好な職場の人間関係のために
ケアが必要な方とそのご家族を支えるためには、医療、福祉、地域(行政含む)と多職種の連携が必要となります。
多職種連携を行う場合、個々の立場での、こうある「べき」が異なることから、お互いのにイライラが募ることもあります。
アンガーマネジメントは怒りが生まれるのは個々の「べき」と現実の間にギャップが生じるからだと考えます。
医療職には医療職の「べき」、福祉、介護職には福祉、介護職の「べき」、地域には地域の「べき」があります。
そして、ご本人、ご家族にも大切な「べき」があります。
どれも重要な「べき」だからこそ、それぞれの立場を尊重し、「一人の方をケアするためには、【こうあるべき】
のすり合わせをしてチームケアとしての目標を定めなければなりません。
それぞれの「べき」をまとめ、よりよい介護のチームケアを行うためにも、アンガーマネジメントは必要です。
また、施設で勤務する職員さんたちの場合、職場のチームマネジメントにもアンガーマネジメントは役立ちます。
自分とケアのやり方の違うスタッフへのイライラや新しく入ったスタッフへの指導でイライラする、
といった現場の声をよく聴きますが、お互いの「べき」を認め合う事で、スタッフ同士での相互理解が深まり
目の前におられるケアが必要な方への関わりがより質の良いケアに変わっていくでしょう。

自ら介護職員として、アンガーマネジメントの重要さを感じる日々
私も日々、介護現場で勤務していますが、アンガーマネジメントを学び、実践を続けてきたことで
仕事に対する考え方も変化したと感じています。
以前は、落ち着かない利用者さんに対してイライラしてしまう事が多かったのが、
自分がイライラする事で利用者さんも落ち着かなくなってしまうのでは?と気付きました。
もちろん、今でもついイライラしてしまう事もありますが、アンガーマネジメントのトレーニングを
繰り返すことで気付きを多く得られています。
講座情報はコチラ:
https://www.angermanagement.co.jp/seminar
現在、日本アンガーマネジメント協会ではオンライン講座も開催しています。